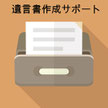☘ ご挨拶
行政書士渡辺事務所のHPをご覧いただきありがとうございます。当サイトは以下の方のために開設しています。
■ 遺言書の書き方について知りたい。
■ 遺言を書いてみた。不備がないか確認してほしい。
■ 法務局の自筆証書遺言保管制度を使って遺言を作りたい。
■ 公正証書で遺言書を作りたい。
■ 「相続」について知りたい。
■ 遺産分割協議書案を書いてみた。専門家にみてもらいたい 。
■ 相続があったが預貯金がおろせない。手続きを頼みたい。
■ 離婚協議書の書き方について知りたい。
■ 離婚協議書案を書いてみた。専門家にみてもらいたい 。
■ 公正証書で離婚協議書を作りたい。
☘ 「全国対応」どこからでもお申込みが可能です。
☘ 気になるニュース 》 アーカイブ
共同親権法案 きょう成立 公布から2年以内に施行する。
今回の改正案では、父母双方が親権を持つことが選択可能になる。父母の協議で決めるが、折り合わなければ家裁が判断する。DVや虐待の恐れがあれば、単独親権とする。既に離婚した父母も共同親権への変更申し立てが可能。共同親権下でも「急迫の事情」や「日常の行為」に当たる行為は、単独で親権を行使できると規定。・・・
改正案は他に、続発する養育費不払いへの対策として、離婚時に取り決めがなくても最低限の支払いを義務付ける「法定養育費」を創設。・・・(2024.5.17東京新聞2頁)
□成年後見人期間制導入も 法相、諮問を表明 利用促進狙い
・・・現行では、後見制度を利用すると事実上亡くなるまで中止できない。弁護士らの専門職には報酬支払が必要で「負担が重い」との声がある。法制審では一定の期間や、相続の取り決めなど、ライフイベントの完了時点で利用を終了できる仕組みの導入を検討する。・・・「身の回りの世話が必要になったので、弁護士から福祉関係者に引き継ぐ」など交代を柔軟に認める是非を探る。後見人には財産管理など強力な代理権があり「後見人の反対で、利用者が望む家族旅行に行けなかった」といったトラブルが起きている。利用者の判断能力に応じ、代理権を制限するかどうかも議論の対象となる。
15日の法制審ではこのほか、自筆の場合は本文の全文手書きが義務付けられている遺言に関し、パソコン入力などデジタル方式で作成することを認める制度見直しを諮問する。(2024.2.14東京新聞23頁)
□共同親権導入へ 法制審要綱案 法定養育費を創設
・・・現行民法を改め、共同親権を選べるようにする。・・・(離婚時に取り決めていなくても)必ず支払うべき「法定養育費」を創設する。(2024.1.31東京新聞3頁)
□ 農地取得 国籍届出 経済安保外国人所有を把握 来月から
農林水産省は9月から、農地を取得する際の申請項目に「国籍」を追加することを決めた。外国人の農地所有について「より的確に実態を把握する」(野村哲郎農林水産相)ためで、経済安全保障の観点から外国人の農地取得の把握を強化する。農地法施行規則を改正する省令案に明記した。9月1日から施行する。個人や法人が農地を取得するには市町村の農業委員会に申請し、許可を受ける必要がある。施行後は個人の国籍のほか、法人の場合も設立した国や大株主の国籍などを届け出てもらう。・・・(省略) ・・・。
今週から自治体の申請があれば企業の農地保有がしやすくなる・・・(省略) ・・・。(2023.8.4朝日新聞3頁)
□ 保険証廃止マイナー一体化 改正法成立 来秋から活用範囲拡大も
保険証をマイナンバーカードに一体化させることなどを盛り込んだマイナンバー法など関連の改正法が2日、参議院本会議で賛成多数で可決、成立した。・・・(省略)・・・。
現行の保険証は、24年秋の開始から一年間は経過措置としてとして有効となる。・・・(省略) ・・・。
この他改正法では、12桁のマイナンバー(個人番号)と年金受給者の預貯金口座を紐づける制度も新設する。・・・(省略) ・・・。給付金などを受け取る公金受取口座として登録する。・・・(省略) ・・・。(2023.6.3朝日新聞3頁)
無縁遺骨にならないために・・・
1⃣市区町村の終活制度を確認 自治体により対応が異なるため、市区町村の地域包括支援センターなどに問い合わせる・・・
2⃣民間機関に相談 各地の行政書士会が開く終活相談会などを活用。葬儀社や寺院は生前契約を結べるところも
3⃣遺言などに明記 遺言書を作る場合は、受遺者や遺言執行者を指定し、火葬、納骨などの死後事務委任契約を結ぶ。指定した人の了承を受けておくことが大事
4⃣つながる努力 自分が住む地域とつながることを意識する。支援するNPOがある地域も(2022.12.30朝日新聞2頁)
□ 生前贈与 加算期間延長 23年度税制改正 死亡前3年から7年に
政府与党は2023年度の税制改正で贈与税のルールを変更する方針を固めた。多くの人が生前贈与で使う贈与税の課税方式「暦年課税」についは、贈与額を相続財産に加えて相続税の対象とする期間を今の死亡前3年を7年に延ばす方針だ。・・・「相続時精算課税」についても・・・生前贈与を受けるたびに少額でも税務署への申告が義務付けられており、手続きが煩雑なことから・・・年110万円までなら申告不要(非課税)とする方針だ。・・・(2022.12.13朝日新聞7頁)
□ 再婚後出産「現夫の子」 嫡出推定見直し 改正民法が成立 ・・・10日、参院本会議で成立した。2024年夏までに施行される。・・・また、・・・「懲戒権」規定が削除された。・・・(2022.12.11朝日新聞1頁)
□ 共同親権と単独 併記 法制審試案 賛否対立 ・・・法務省は年内にもパブリックコメントを実施して国民の意見を募る。・・・(2022.11.16朝日新聞1頁)
□ 嫡出推定見直し閣議決定 民法改正案 親の懲戒権削除も
・・・今の臨時国会に提出し、成立を図る。
民法改正案の骨子 ・離婚後300日以内に生まれた子でも、再婚後に生まれた場合は、「前夫」ではなく「現夫」の子に ・離婚後100日間の女性の再婚を禁じる規定を廃止 ・(子への)「懲戒権」を削除し、体罰の禁止を明記・・・(2022.10.15朝日新聞1頁)
□ 100歳以上9万人突破 最高齢は115歳 ・・・厚生労働省が16日発表・・。女性は・・・全体の約89%・・・。・・・。100歳以上の高齢者は、・・・1963年は153人・・(2022.9.17朝日新聞35頁)
□ 離婚後の共同親権 選択肢 法制審たたき台 単独親権と併記
ー法制審議会(ー)の部会は19日、「共同親権」の導入と、現行の「単独親権」の維持を併記する形で論点整理した。・・・共同親権を導入する場合は、「原則=共同、例外=単独」とする案と「原則=単独、例外=共同」とする案を提示。・・・(2022.7.20朝日新聞3頁)
今春2022年4月1日に改正民法が施行され18歳以上が成人となりました
ℚ 18歳になったら何ができるようになる?
A ①親の同意が不要な契約 例えば・・・携帯電話の契約、クレジットカードを作る、車やバイクの購入、ローンを組む
②10年間有効のパスポートを作る③仕事を自分の意志で決められる
④裁判員を務められる⑤住む場所を自分で決められる
⑥行政書士、公認会計士、司法書士等の国家資格の取得
⑦性同一障害について性別の取り扱いの変更の審判を受けられる
⑧(省略)⑨NISAの利用(2023年1月1日~)⑩国籍の選択 など
ℚ 法律が変わっても20歳以上になるまではできないものもある?
A ①飲酒、喫煙 ※健康面への影響、非行防止などの観点から
②競馬や競輪、オートレースなどのギャンブル(公営競技)
③猟銃の保持④投資を迎える⑤中型、大型自動車免許の取得
ℚ 女性の婚姻開始年齢は変わった?
A 女性の婚姻開始年齢は16歳から18歳に変わりました。(男女ともに18歳となり親の同意は不要)
ℚ 18歳から成人になって特に気をつけなければいけないことは?
A ①交わした契約に対し責任を負う(未成年を理由とする契約解除ができなくなった)②起訴されたら顔と実名が報道される
ℚ 今までと変わらないことは?
A 普通自動車免許の取得②男性が結婚できる年齢③選挙権(平成27年から18歳に改正済)④少年法の適用(ただし、18歳、19歳は「特定少年」となり、17歳以下とは異なる取り扱い⑤国民年金の加入年齢
ℚ 成人式はどうなる?
A 成人式の時期やありかたに関しては、法律による決まりはありません。各自治体の判断で成人式は実施されます。
(出典:2022.4.1彩りコミュナスVol.20 4.5頁)
□ 嫡出推定 民法見直し 再婚後出産「現夫の子」に 法制審答申
法制審議会は14日、・・・法相に答申した。(2022.2.15朝日新聞1頁)
14日はほかに4件の答申が行われた。1件は、子に対する親の「懲戒権」を定めた民法の規定の見直し。しつけを口実にした虐待を防ぐため、懲戒権を削除したうえで新らたに、親に対して「子の人格の尊重」などを義務づけ、体罰をはじめ「心身の健全な発達に有害な影響を及ぼす言動をしてはならない」と明記することが盛り込まれた。・・・(2022.2.15朝日新聞3頁)
□ 再婚後なら「現夫の子」 法制審部会答申案 嫡出推定見直し
結婚や離婚の時期によって生まれた子の父親が誰かを決める「嫡出推定」の規定について、法制審議会(法相の諮問機関)の部会が1日、見直す内容の答申案をまとめた。離婚300日内に生まれれば「前夫の子」とする現行の規定に、「再婚後なら現夫の子」とする例外を加える。出生時の夫婦が両親だとみなされるようになることに伴い、離婚後100日間の再婚を女性に禁じた規定もなくす。
・・・近年、夫の暴力から逃れて別居中に別の男性との間に子ができた場合など、「前夫の子」とされるのを避けたい母親が出生届を出さないまま子が無戸籍になっていることが問題化。・・・
このほか、父子関係を否定する「嫡出否認」の権利を父親のみから子や母親にも広げる。・・・、父親から否認への協力を得られない場合でも、母親らが「前夫の子でない」とすることを可能し、出生を届けやすくする。
(2022.2.2朝日新聞3頁)
□ 30年増えぬ賃金 日本22位 上昇率は4.4% 米47% 英44% ・・・2020年の日本の平均賃金は、・・・424万円。
・・・1位米国(736万円)・・・韓国・・・15年に抜かれ、いまは38万円差だ。・・・19年の1人あたりの労働生産性は37カ国中26位。(2021.10.20朝日新聞1頁、13頁)
□ 預金引き出し 認知症への備えは 代理人 先に指定できるサービス
三菱UFGフィナンシャルグループは、「予約型代理人サービス」を3月下旬から始めた。同行の顧客が、認知・判断能力の低下に備え、あらかじめ金融取引の代理人を指定できるサービスだ。・・・。ポイントは、代理人取引が可能となる時期。・・・金融取引の判断が本人では難しくなった後から、となっている。・・・(2021.6.9朝日新聞21頁)
□ 所有不明の土地抑制法成立 ・・・21日、参院本会議で可決、成立した。法改正で相続時の登記を義務づけて違反に過料を科す一方、・・・相続人が土地を手放せる制度を規定した。それぞれ公布から3年以内、2年以内に施行される。
見直し案では、・・・相続人が取得を知った日から3年以内の相続登記の申請を義務化。違反に10万円以下の過料・・・。所有者の転居に伴う住所変更などの際にも2年以内の変更登記の申請を義務づけ、罰則は5万円以下の過料・・・。(2021.4.22朝日新聞31頁)
婚姻・離婚届 人生の節目「ハンコ必要」の声 押印欄 希望者向け存続
・・・婚姻・離婚届などの戸籍関連の手続き。・・・住民票の転入・転出届(総務省所管)では、押印が必要なくなる見通し・・・(2021.3.23朝日新聞3頁)
「養育費請求は子の権利」検討 法制審、民法明記議論へ
・・・支払いに関する事前の取り決めを親に義務づけ、取り決めがなくても法定額の請求を可能とする仕組みの導入も論点となる。・・・(2021.3.23朝日新聞1頁)
□ 所有者不明の土地を増やさない 法制審答申 相続登記を義務化 違反に過料
・・・法制審議会は10日、相続や住所変更時の登記を義務付け、違反すれば過料の対象となることなどを内容とする法改正を上川陽子法相に提出した。 ・・・・・・
望まない相続も相次ぐことから、答申では、相続人が取得した土地を手放せる制度を創設する。・・・要件を満たし、10年分の管理費相当額を納付すれば、所有権を国庫に帰属させ・・・。(2021.2.11朝日新聞1頁)
□ 嫡出推定「再婚後なら夫の子」 法制審試案 離婚後300日以内に例外規定
・・・法制審議会の部会は9日、答申の中間試案をまとめた。「離婚後300日以内に生まれた子は前夫の子」とする規定の例外として「再婚後なら夫の子」と新たに規定する。「前夫の子」とされることを避けたい母親が出生届を出さず、こが無戸籍になる問題の解消を図る。
・・・・・・
中間試案では、・・・、父子関係を否定する「嫡出否認の権利を父親のみから未成年の子にも拡大し、子の代わりに母親が行使する仕組みを検討することも盛り込まれた。例外規定にあたらず、父親から否認の協力を得られない場合でも、母親側で「前夫の子でない」とすることを可能にし、出生を届け出やすくする。
さらに、近年では妊娠を機に結婚する夫婦も多い実態を踏まえ、「夫の子」とする範囲を「結婚から200日を経過後に生まれた子」から拡大し、「結婚前に妊娠した子でも結婚後に生まれた子は夫の子」と規定する。・・・
現行の制度では、仮に女性が離婚後すぐ再婚し、201から300日以内に子どもが生まれると、前夫と夫で父親の「推定」が重複する。これを避けるため100日間に限って女性の再婚禁止が設けられているが、見直しで重複が解消されることから、中間試案では(女性の再婚禁止期間)規定そのものを削除するとした。(2021.2.10朝日新聞3頁)
☘ 最近の民法等の改正
□ 成年年齢の18歳への引き下げ 2022年4月1日施行
□ 婚姻適齢(結婚することができる年齢)統一 現行男18歳、女16歳を、18歳に統一(2022年4月1日から)
□ 債権法(民法債権編)改正(2017.6.2公布、2020年4月1日施行)
■ 保証人の保護に関する改正
1. 極度額の定めのない個人の根保証契約は無効となった。
2. 事業用の融資の保証人に個人がなる場合は、契約締結の1か月以内に、公正証書によって保証意思を表示することが義務付けられた。これがない契約は無効となった。
3. 情報提供義務の新設
① 契約締結段階では、主たる債務者は、保証人に対し、「財産及び収支の状況」「主たる債務以外に負担している債務の有無及び履行状況」「主たる債務の担保として他に提供し、又は提供しようとしているもの」の情報を提供しなければならないこととなとなった。
② 保証債務の履行前の段階では、主たる債務者は、保証人から請求があった場合は、 主たる債務の支払い状況について情報を提供しなければならないことととなった。
③ 債権者は、債務者が期限の利益を失ったときは、2か月以内に保証人に通知しなければならないことととなった。
■ その他の改正
4. 新たに定型約款の規定が設けられた。
5. 法定利息を5%から3%に引き下げ、市中金利変動制を導入した。
6. 業種別の1年から3年の短期消滅時効を廃止し、消滅時効は原則5年に1本化した。
7. 意思能力を有しないでした法律行為は無効であることを明文化した。
8. 将来債権の譲渡(担保設定)が可能であることを明文化した。
9. 賃貸借終了時の敷金返還や原状回復に関するルールを明文化した 。
10. 「錯誤」による意思表示の効果を「無効」から「取消し」に改めた。今後は「取消し」の主張期間の制限を受ける。
■ 詳しくは、》債権法改正 をご覧ください。
□ 改正民事執行法が施行され、令和2年4月1日以降は、養育費の取り立ては強制執行認諾条項付公正証書に基づいて裁判所に申し立てれば、元配偶者の勤務先情報、預貯金口座のある金融機関の支店名不動産などの財産関連の情報を入手できるようになりました。 法改正前に作成された公正証書であっても可能となります。
改正前は、強制執行認諾条項付公正証書による履行強制の場合は、財産開示請求制度を利用することはできず、自分で元配偶者の口座がある銀行の支店を探して法務局などで銀行の代表者事項証明書などを取得する必要がありました。
□ 相続法の改正(2018.7.13公布)
1. 「配偶者居住権」「配偶者短期居住権」の創設
2. 婚姻期間20年以上の夫婦相互間における自宅の贈与は、特別受益持戻しをしない。(生前贈与・遺贈した自宅は遺産分割の対象から除かれることとなった)
3. 「預金の仮払制度」創設(遺産分割前でも預貯金の払い戻しができるようになった)
4. 遺留分減殺請求権の金銭債権化(遺留分減殺請求権から遺留分侵害額請求権に変更され、遺留分侵害額請求は金銭で支払うことに限定された)
5. 相続人への生前贈与については、死亡前10年間にされたものに限り、遺留分算定の対象財産に算入するようになった。
6. 「相続させる」遺言による不動産登記関係(不動産の相続に関し、法定相続分を超える部分については登記をしなければ第三者に対抗できないことになった )
7. 遺言執行者の権限の明確化等がなされた。
8. 「特別の寄与」の制度の創設(「特別の寄与」の制度の創設され、相続人以外でも療養看護等を行った場合は金銭を請求できることになった)
9. 自筆証書遺言の一部をワープロ等で作成可になった。
10. 自筆証書遺言を保管する制度の創設(2020年7月10日施行)
■ 詳しくは、》相続法改正 をご覧ください。
□ 成年後見制度の改正(2016.4.13公布・10月13日施行)
改正法では、成年後見人は、成年被後見人の死亡後にも、個々の相続財産の保存に必要な行為、弁済期が到来した債務の弁済、火葬又は埋葬に関する契約の締結等といった一定の範囲の事務を行うことができることとされ、その要件が明確にされた。
□ 離婚した女性の再婚を禁じる期間が従来の6カ月から100日に短縮(100日以内でも、離婚時に妊娠していないことを医師が証明すれば認める)(2016.6.1 民法改正)
□ 2013年(平成25年)9月5日以後に開始した相続について嫡出でない子の相続分も嫡出子と同等となった。
2013年(平成25年)9月5日前に被相続人が死亡した場合も、2013年(平成25年)9月5日以後に開始した「相続」については、嫡出でない子の相続分も嫡出子と同等となった。
2001年(平成13年)7月から2013年(平成25年)9月5日までの間に開始した「相続」については、「確定的なものとなった法律関係」に該当しない場合には、嫡出でない子の相続分も嫡出子と同等となる。
|
Q. 行政書士の業務は? ➤ 答え |
☘ Coffee Break 》写真ギャラリー
| □ お役立ち情報 |
![]() 遺言状の書き方講座
遺言状の書き方講座
♧遺言状作成の準備
♧遺言作成のポイント
♧遺言文・別紙遺産目録の書き方
➤相続人(受遺者)・受贈者(遺言で贈与を受ける者)の定義(特定)の仕方
♧遺言が特に必要な人は
♧遺言にはどんな種類があるか
♧遺言できる者、遺言の効力
➤遺言能力
♧遺言できること
➤付言事項
☘個別遺言事項
➤ 内縁関係での「相続」 (再掲)
➤ 遺言による指定分割(遺言による遺産分割の実行の指定)(再掲)
➤法定相続分と指定相続分(再掲)
➤法定相続人、法定相続順位(再掲)
➤遺贈
➤遺贈寄付
➤死因贈与
☘財産をあげる予定の人が先に亡くなった場合に備える
➤補充遺贈
♧ 完成したらチェック
♧遺言を取り消すには?
♧遺言書の検認
![]() 相続について法律で決まっていること
相続について法律で決まっていること
♧相続する人や分け前は法律で決まっています
➤遺言による指定分割(遺言による遺産分割の実行の指定)(再掲)
➤遺言による推定相続人廃除(再掲)
➤遺留分
➤ 特別縁故者
♧被相続人(親)より先に子が死亡したら孫が相続します
➤代襲相続
➤同時死亡の推定~遺言者と相続人が死亡しその先後が明らかでないとき~
♧多額の借金がある場合は相続を放棄できます
➤相続放棄
➤限定承認
➤単純承認
➤財産分離
♧世話をした人は遺産等をもらえます
♧生前に特別にお金をもらっていたら相続分が減らされます
➤特別受益
♧2018相続法改正
![]() 遺産分割と遺産分割協議書
遺産分割と遺産分割協議書
♧遺産分割とは
♧協議による遺産分割はどう進めるか
♧相続財産
➤生命保険金・死亡退職金・退職年金・未支給年金・遺族年金・個人年金と遺産分割
➤配偶者居住権(再掲)
♧遺産の分配方法
♧遺産分割協議書の書き方
♧数次相続
![]() 遺言執行と遺言執行者
遺言執行と遺言執行者
♧遺言執行について
♧遺言執行者について